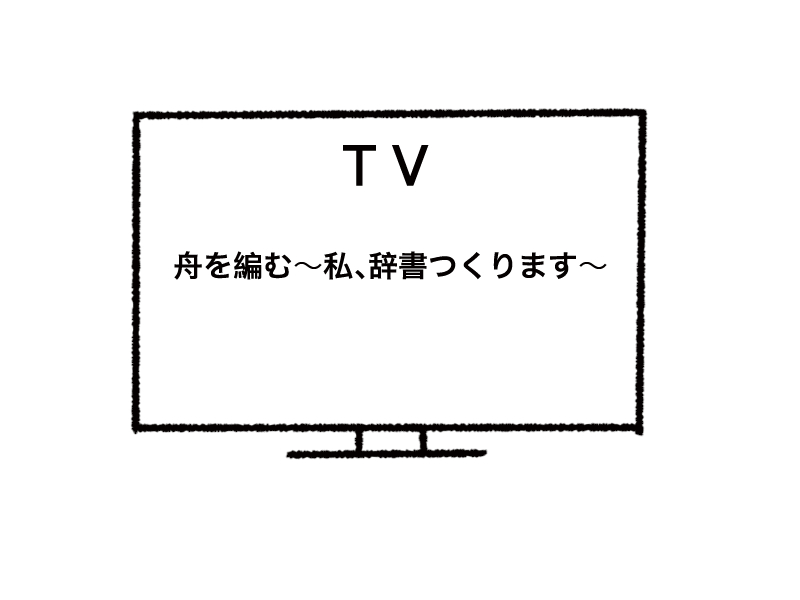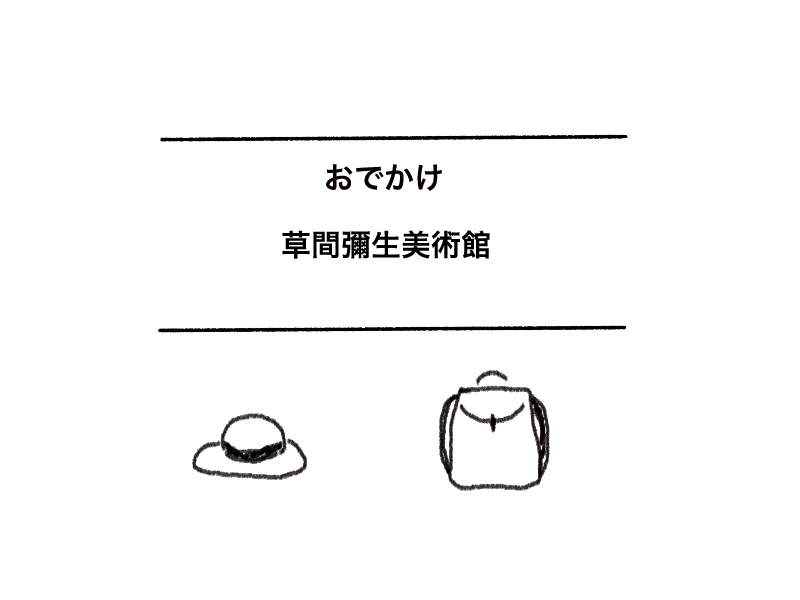「舟を編む」は映画にもなっていて、そちらもいいのですが、NHKの火曜日のドラマ枠で放送されているこの番組も素敵です。
突然ファッション編集部から辞書編集部に異動になった女性主人公。
数年かがりで編集中の「大渡海」という日本語の中型辞書をつくるのがミッション。
編集会議で、雑誌はそこに書いた言葉が世の中を動かすことがある、辞書もそれでいいのではと主張する主人公、しかし、長年辞書づくりに携わってきた編集者からは、言葉は消えていってしまうこともある。辞書には、残る言葉を採録すべきなのだと諭される。もちろん、辞書に載っても消えていく言葉もあるのでしょうが。
同じ出版社の編集部門でも、作っているものが違うとこれだけ考えるべきことが違う。同じ会社から発行される印刷物を作っていても、ものづくりに対する姿勢が全く異なる。
生きることはすなわち変わること。だから、生きている人の名前は採録しない。
すぐに消えてしまうものを作るのか、それとも、時代を映しながらも人々の拠り所となるものをつくるのか。
辞書編集者たちは、ひとつひとつの言葉について、それがどういうものか、何を表すものなのか、真剣に向き合います。
ものづくりの大変さ、大切さがよくわかります。
そして演出も素敵。
空からキラキラと言葉が降ってきたり、言葉がピカピカと光を放ったり。
日本語、美しいですね。そして、難しい。