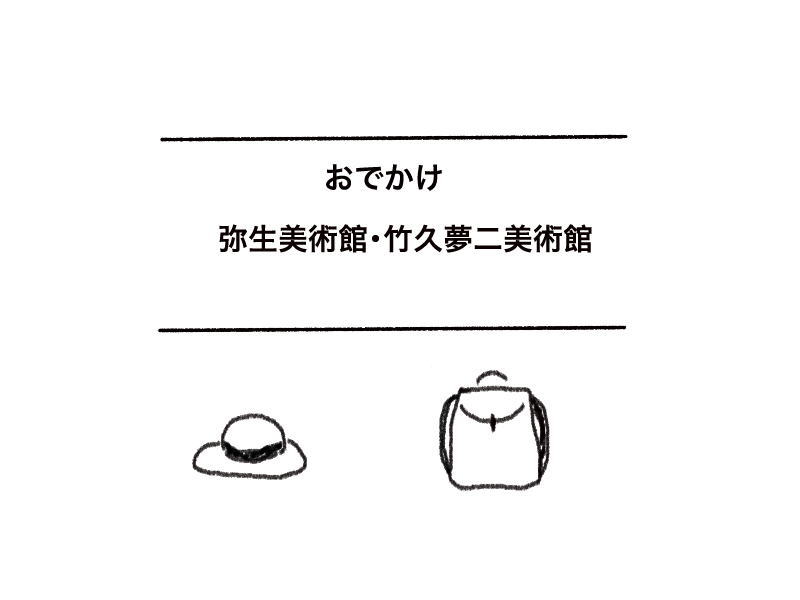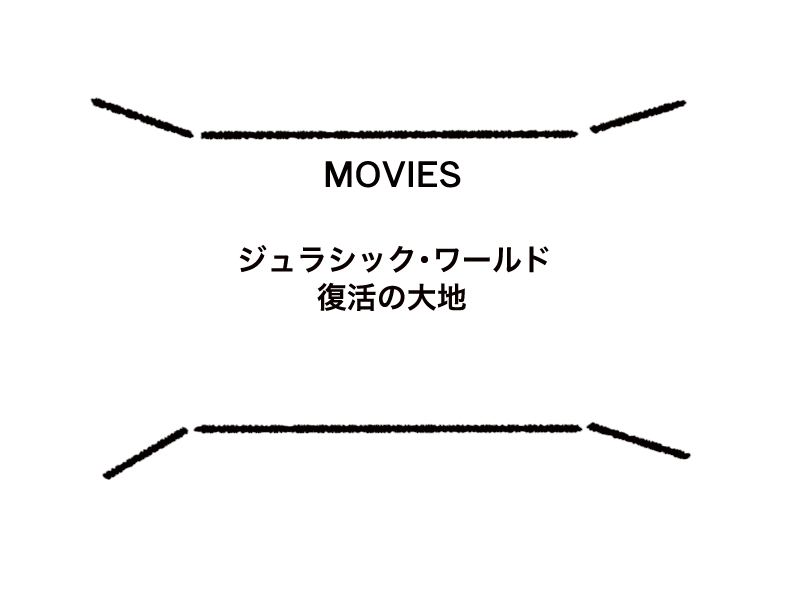東京大学の裏側にひっそりと佇む美術館です。住所は東京都文京区弥生。弥生式土器が出土したあたりでしょうか。
私が訪れるのは2回目。前回は2年ほど前、「大正の夢 秘密の銘仙ものがたり展」でした。大正から昭和初期に女学生を中心に大流行した銘仙を集めたもの。当時の銘仙は、かなり斬新な色や柄で、当時がいかに華やかで自由な気風に満ちていたのかが想像できました。
明治維新以降、日本は何度も戦争をしてきたわけですが、第二次世界大戦で痛烈な敗北を味わった日本。しかし敗戦後は奇跡の高度経済成長ととげ、私はまさに高度経済成長の真っ只中に生まれたわけですが、もはや戦後は終わったと誰かが宣言したその後であったはずながら、まだ、戦争に負けて貧しくなった日本の姿もそこかしこに見え隠れしていました。なので、メタメタになった昔の日本、のさらに向こう側に、そんな華やかな時代があった、ということはなんとなく想像が難しかったように思います。
しかし、美しいものを追い求めることができて、斬新な柄も着こなすことが許される、そんな時代が昔の日本にはあったんですね。でもすぐその後、贅沢は敵だなどと言われる時代がやってくる。うっかりするとそんなことになってしまうんだな、とも思いました。
そして今回。「ニッポン制服クロニクル」では、これまでの学生服の変遷と今後どうなっていくのか、という展示でした。
まず基本形。男子は詰襟、女子は、セーラー服、ジャンパースカート、ブレザーとスカートの基本的な制服。真面目な子たちはそんなスタイルでしたね。
その後、変形学生服の展示。ツッパリやスケバンたちがしていたスタイルです。男子は長ランあるいは短ランにボンタン、女子はスカートを長くしていましたね。カバンは潰していました。確か、「3年B組金八先生」というドラマで、「学ラン長ラン大混乱」というタイトルの回があり、そこで近藤真彦演じる学生が学校に長ランをきてくるという話があったと思います。あれです。マネキンは頭がありませんでしたが、男子はリーゼント、女子はソバージュでしたでしょうか。
そして、男子がズボンを下げ、女子はミニスカートとルーズソックスの時代がやってきます。コギャルの時代。渋谷界隈にはヤマンバギャルと言われる子たちが出没していましたね。当時の女子生徒たちはスカートを短くするためにウエストの部分を織り込んでいたようですが、それができないようなデザインのものもあったんですね。初めて知りました。
併設展は、高畠華宵の作品と、「夢二とたどるアール・ヌーボーとその周辺」でした。
いつも、ちょっと素敵な企画展をやっています。併設のカフェのカレーも美味しいです。こぢんまりとした美術館ですが、独特の雰囲気があってほっこりします。